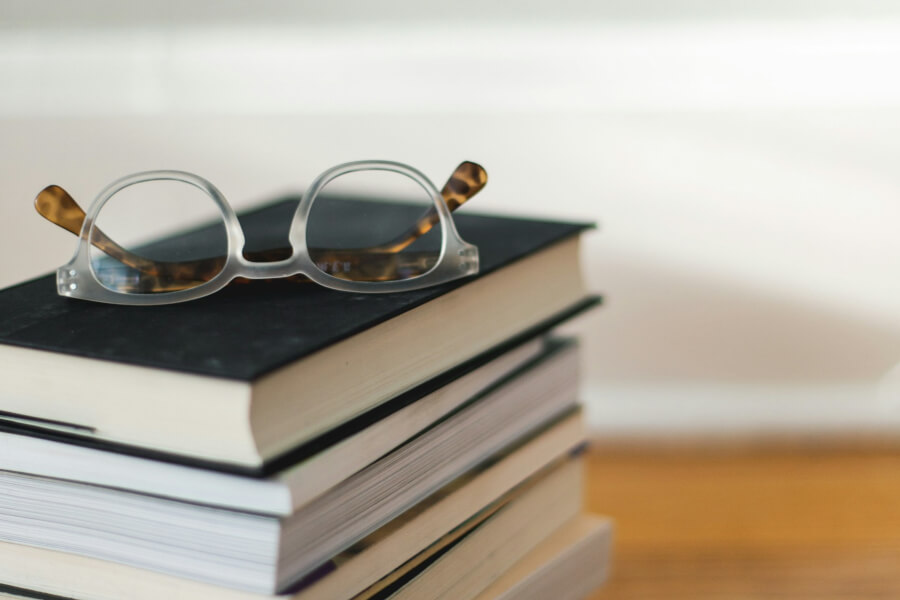
過去問が最重要なことは事実だが、その中でも取捨選択をすべき
過去記事でも何度か書いてきたとおり、資格試験対策において最も重要視すべきなのは「過去問」です。
最低でも直近5~10回分、可能ならさらに集められる限りの過去回の過去問を入手して、一通り目を通しておくことが望ましいです。
しかし、過去問で出たところは漏れなく完璧に理解しておくべき、というわけでは必ずしもありません。
むしろ、過去問の中でも、「特に注力すべきところ」と「捨ててもよさそうなところ」は適切に取捨選択すべきです。
ポイントは、「過去問の中でももう二度と出なそうな細かすぎるところは思い切って捨てる」ことです。
多くの資格試験では、「こんなに細かいところまで覚えてる人はそういないだろう」と思えるような、いわゆる「重箱の隅をつつくような問題」が一定程度は出るものです。
過去問題集というのは基本的に各回の出題内容をそのまますべて収録しているものなので、当然ながら「重箱の隅系問題」も収録されていますが、これらも含めてすべてを完璧に理解・暗記しようとすることは勉強量が過大になりすぎて、勉強の効率を大きく落とす結果にもつながりがちです。
しかし、このような問題の割合は多くてもせいぜい全体の1~2割程度です。
残りの8割以上は「過去問と同じような内容が繰り返し出ている問題」や「過去問とまったく同じではないが、過去問を普通に解けるくらいの知識があればそれを応用してなんとか解けるくらいの問題」です。
一般的な資格試験の合格ラインは「正答率6割~8割」程度なので、「重箱の隅系問題」が解けなくても合格ラインはじゅうぶん超えることができます。
過去問を勉強していて「重箱の隅系問題」まですべてマスターするには負荷がかかりすぎると感じる場合は、思い切って捨てて基本問題に注力するのが得策です。
とはいえ、過去問で出てくる問題が「重箱の隅系問題」だといえるかどうかは、ある程度勉強が進んだ段階でないとなかなか見極めが難しいかもしれません。
過去問題集によっては問題ごとに「難易度」「重要度」「頻出度」といった項目をABCや★の数などで評価している本や、「本試験での全受験者の正答率」のデータを記載している本もありますので、そのようなタイプの過去問題集を優先的に使ってみるのもよいでしょう。
また、いわゆる「精選過去問題集」という、重要度が高い過去問(≒同じような問題がまた出る可能性が高い過去問)のみを厳選したタイプの過去問題集が出ている場合もあるので、こういった参考書もぜひ活用してみてください。








